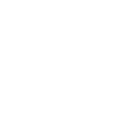聴き放題対象
チケット対象
松尾匡【講演CD:市場主義時代に見直す「江戸商人道」】
出版社 暦日会、パワーレクチャー
ナレーター松尾匡(立命館大学教授)
再生時間 01:06:52
添付資料 なし
販売開始日 2010/4/26
トラック数 3
作品紹介
松尾匡 【講演CD:市場主義時代に見直す「江戸商人道」】
江戸の商人道からビジネスの真髄を学びましょう!今の時代を乗り切るために、商売の基礎である「売り手良し、買い手良し、世間良し」に立ち返ってみましょう。
経済学者である松尾匡氏は本来、ゲーム理論を使って社会システムを分析するのが専門だ。
ここでは武士道を身内集団倫理、
商人道を開放個人主義倫理として位置づけ、
この2つの倫理を踏まえて最近の経済事象や社会現象を説き起こす。
その上で江戸時代の商人道について武士道と対比しながら、
代表的な思想家や商人を例にその特徴を解説。
江戸時代の武士道精神から見た商行為は
「非道なことで買い手を食い物にするもの」とみられ、
社会階級でも「士農工商」として最下位に置かれた。
これに対して18世紀に京都中心に活躍し商人道を体系化した思想家の石田梅岩。
彼は商取引と利潤を肯定し「商人道は悪いことではなく正義であり、
天下の人々に尽くす善行である」とした。
商人が「他人のために尽くして利潤を得るのは、
武士が主君のために尽くして俸禄をもらうのと同じ」と解釈し、
特に正直と公正を重んじたという。
さらに身内びいきを戒め他人に対しては返礼を期待せず、逆に施す。
倹約と勤労を旨とし、それ自体が自己目的と説いた。
この思想に共通するのが近江商人で
「売り手良し、買い手良し、世間良し」とする「三方良し」の思想である。
行商先の他国でも常に他者意識を忘れず周囲に対して気を遣うこと。
勤勉、節約、忍耐を自己目的とし、さらに社会貢献にも努めたとされ、
当時の大丸、住友、安田財閥などの例を紹介。
明治時代以降は商人道精神を逸脱して武士道型倫理に向かう。
しかし「商人道精神は脈々と生き続けており、
今こそ商人道精神を意識して困難な時代を乗り越えることが大事」と説いた。
江戸の商人道からビジネスの真髄を学びましょう!今の時代を乗り切るために、商売の基礎である「売り手良し、買い手良し、世間良し」に立ち返ってみましょう。
経済学者である松尾匡氏は本来、ゲーム理論を使って社会システムを分析するのが専門だ。
ここでは武士道を身内集団倫理、
商人道を開放個人主義倫理として位置づけ、
この2つの倫理を踏まえて最近の経済事象や社会現象を説き起こす。
その上で江戸時代の商人道について武士道と対比しながら、
代表的な思想家や商人を例にその特徴を解説。
江戸時代の武士道精神から見た商行為は
「非道なことで買い手を食い物にするもの」とみられ、
社会階級でも「士農工商」として最下位に置かれた。
これに対して18世紀に京都中心に活躍し商人道を体系化した思想家の石田梅岩。
彼は商取引と利潤を肯定し「商人道は悪いことではなく正義であり、
天下の人々に尽くす善行である」とした。
商人が「他人のために尽くして利潤を得るのは、
武士が主君のために尽くして俸禄をもらうのと同じ」と解釈し、
特に正直と公正を重んじたという。
さらに身内びいきを戒め他人に対しては返礼を期待せず、逆に施す。
倹約と勤労を旨とし、それ自体が自己目的と説いた。
この思想に共通するのが近江商人で
「売り手良し、買い手良し、世間良し」とする「三方良し」の思想である。
行商先の他国でも常に他者意識を忘れず周囲に対して気を遣うこと。
勤勉、節約、忍耐を自己目的とし、さらに社会貢献にも努めたとされ、
当時の大丸、住友、安田財閥などの例を紹介。
明治時代以降は商人道精神を逸脱して武士道型倫理に向かう。
しかし「商人道精神は脈々と生き続けており、
今こそ商人道精神を意識して困難な時代を乗り越えることが大事」と説いた。
新着作品
週間総合ランキング
読み込み中...